導入事例
学修用の「頭蓋骨比較アプリ」「頭蓋骨パズル」を開発
鶴見大学様
鶴見大学歯学部様(神奈川県横浜市)では、学生が頭蓋骨の構造を視覚的に理解できるよう、三谷商事と連携して「頭蓋骨比較アプリ」と「頭蓋骨パズルアプリ」を開発しました。頭蓋骨の複雑な構造も直感的に理解することができ、歯学教育の現場に新たな学びのスタイルをもたらしています。
頭蓋骨の構造を視覚的に理解できる学修アプリを開発
神奈川県横浜市に位置し、文学部と歯学部の2学部を有する鶴見大学様。同大の歯学部では、学生が視覚的に頭蓋骨の構造を理解できるよう、三谷商事と連携して「頭蓋骨比較アプリ」「頭蓋骨パズルアプリ」を開発しました。
本教材の開発を主導したのは、歯科矯正学を専門とする友成博教授と、歯科法医学を専門とする勝村聖子教授です。開発のきっかけとなったのは、学生と接する中で感じた、とある課題でした。
「最近の学生は視覚的な情報処理に長けている一方で、本や教科書で学修するのが苦手な傾向にあるように思います。そこで、パッと見て視覚的に理解を深められるような教材を作ろうという発想からスタートしました」(勝村教授)。
その後、2022年ごろに三谷商事に相談し、開発がスタート。まずは学生に身体の仕組みについて関心をもってもらおうと、チンパンジー、ヘビ、ワニといった動物と人間の頭蓋骨を比較できるアプリを制作しました。たとえば、ヘビの下顎が左右に分かれていて大きな獲物を丸呑みできる構造や、チンパンジーの脳の大きさと頭部形状の違いなどを視覚的に学べる設計になっています。さらに、人間の頭蓋骨も、幼児、成人、高齢者といった年齢別に比較できるよう工夫されています。
「私が学生時代に感動したのは、乳歯が生えている段階で、すでに顎の中で永久歯の“卵”が育っているという画像でした。その驚きと感動を、今の学生にも届けたかったんです」と勝村教授は話します。

歯学部 歯学科 法医歯学
教授
勝村 聖子 氏
二次元ではイメージが難しかった頭蓋骨の解剖学的立体構造をデジタルで学ぶ
一方、友成教授は歯科矯正学の観点から、アプリを活用した三次元教材の効果に注目していました。「歯科矯正学では、患者さんの顎顔面形態の特徴を二次元のレントゲン画像を用いて分析・抽出していきます。しかし、学生にとって二次元の画像から頭蓋顔面の解剖学的立体構造はイメージしづらいんです。頭蓋骨を三次元的に回転させたり、輪切りにしたりして構造を確認できるアプリは、教育的に非常に有効だと感じました」と友成教授は振り返ります。
そこで、頭蓋骨をアプリ上で分解・組み立てながら学ぶことができる「頭蓋骨パズル」を開発。このアプリでは、頭蓋骨を構成する多くの骨の位置関係や名称を、実際に手を動かしながら学ぶことができます。歯科矯正学で必要な基準点や基準面の確認もでき、学生が立体的に頭部構造を捉えることが可能になりました。
専門用語を一般化し理解しやすく「教育現場と開発側が連携できた」
教材開発において、先生方は、技術面はもちろん、三谷商事からの多角的なアドバイスが役立ったと振り返ります。友成教授は「『もっとカラフルに、分かりやすくしてほしい』といった細かな要望にも快く応えていただきました。開発担当の方は非常に理解が早く、教育的な意義を的確に汲み取って提案していただき、とても助かりました」と語ります。
また、専門家にとっては当たり前の表現でも、学生や一般の人にとっては伝わりづらいことが多く、その点でも三谷商事からのフィードバックが役立ったそうです。勝村教授は「たとえば『この角度のヘビの頭の骨って伝わりますか?』というような意見交換も頻繁に行われ、教育現場と開発側がしっかり連携できていたと感じました」と振り返ります。

学修意欲向上に効果大 今後は分野を横断しての活用も
頭蓋骨比較アプリは2年前から導入され、主に1年生の授業で使用されています。授業後に実施したアンケートでは、「立体的に見られるので理解しやすい」「勉強が楽しく感じる」といった声が多く寄せられました。また、同アプリは、AR技術を用いた3Dの空間再現ディスプレイにも展開。まるで実際に目の前で頭蓋骨に触れているかのようなリアルな表現を実現しました。同ディスプレイをオープンキャンパスの際に展示したところ、高校生や保護者から「今はこんなふうに学べるんですね」と好評だったそうです。
頭蓋骨パズルも今年から、順次授業での活用が予定されています。友成教授は「学生にとって、理解できないものは単なる暗記の対象になってしまいます。立体的に理解できるようになれば、学問の楽しさがどんどん深まっていくはずです。三次元的な学修教材は、モチベーションを上げる意味でも非常に効果が高いと感じています。今後は骨のみにとどまらず、筋肉や血管、神経なども可視化できるように発展させていくことで、各専門領域の繋がりを境界なく学習できる一つのツールとして活用できるようになるのではと考えています」と期待を込めました。
三次元的な視点で人体を学び、実感とともに知識を身につけていく。今回の取り組みは、歯学教育の現場に新しい風を吹き込むとともに、学生たちの“学ぶ喜び”を育む新たな一歩となっています。
お客様よりひとこと
医療教育現場とデジタルツールの相性は非常に良いと考えています。デジタル技術を用いて、体験型で学生の理解を深めていくような教育を今後も発展させていきます。

- 歯学部 歯学科 歯科矯正学
教授
友成 博 氏
鶴見大学
- 所在地
- 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3
- 設立
- 1924年4月
- 支店
- 歯学部/文学部/大学院/短期大学部/短期大学部専攻科

営業担当よりひとこと
貴学の新たな取り組みに、ご協力することが出来て光栄です。
今後も、更に教材を増やしていくことで、貴学学生の学修意欲向上並びに、理解度向上に寄与出来ればと考えております。

- 情報システム事業部
東京文教営業部
飯高 晃司

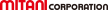

担当者様のコメント
今後も教科書だけでは学べないような、学生の興味を引く学修教材を開発していきたいと考えています。法医学分野でもVRを活用して体感型授業に生かしていきたいです。